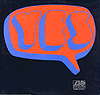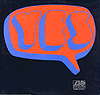Yes First Album
決して傑作ではないのだが、愛すべき作品というものが幾つかある。それは個人的に聞き込む回数の多さから来るのかもしれないし、その作品を聞いた当時の精神状態や状況にも左右されるものであろうことは疑いない。
私がイエスのファーストを好きなのは、もともと英国音楽の地味目の物を好んで聞いていたという嗜好性ばかりでなく、その後傑作を世に出す彼らの、原点としての音楽に対する愛1情が大いに感じられるからに他ならない。
イエスの特徴として現在語られることに、コーラス・ハーモニー;壮大な音宇宙を思わせるダイナミックな空間;テクニック;哲学的な思索を生む詩の世界;複雑なアンサンブル;見事に構築された曲構成・・・と多々あるが、ファーストではどうだろう。
分厚い音は聞かれるし、ハーモニーも豊かだ。しかし後の「こわれもの」や「危機」に表現されるような濃密な音空間という印象は薄い。それじゃあつまらないかというと決してそんなことはないのである。
ユーモラスなバンド・ロゴのジャケットはユニークであるが、彼らのバンド名のイエス(肯定)をそのまま意味するかのように、決してロックとしての反体制を意味するわけではなく、静かに微笑むかのごとく自分たちの存在をアピールするに十分な表現方法であると私は見ている。(因みに米盤ジャケットもメンバーがシンメトリーに配置されていてそれだけで安定感を見せている。英米共にバンドの基本的姿勢を伝える味のあるデザインと評価している。)
彼らはリズムのへヴィさを持ちながら、肝心なメロディを大切にしている。アルバムの冒頭の力強いリフから何か期待させるものがあるが、コーラスパートの繊細さとの対比は実に味がある。ドラムスのビルとベースのクリスのコンビネーションは聞いていて心地よい。ジョンのヴォーカルは結成当初から完成された歌声と言っていい。冒頭の期待感は決して裏切られることなく、緻密な曲構成に当時としての新しさ、意気込みを十分に感じとることが出来る。
この作品と2作目での特徴はカバー曲が聞かれることでもある。ここでは、バーズの「アイ・シー・ユー」とビートルズの「エブリー・リトル・シング」の2曲が取り上げられている。バーズは66年のサイケ色に彩られた「霧の5次元」中の曲で、イエスの演奏もどちらかと言えばオリジナルに近いのがご愛嬌と言ったところか。ただバーズにとっても実験的な意味合いのあった曲なので選曲自体に意外性があって面白い。ビートルズの「エヴリー・リトル・シング」は64年の「フォー・セール」からの選曲。ビートルズにあっては地味な曲をイエスは結構自由にアレンジしている。原曲の基本的なメロディ・ラインは生かしながらも、演奏自体幾分荒っぽく感じさせるのは、当時イエスが影響を受けたと言われたヴァニラ・ファッジの方法論に確かに似ている。ところどころドタバタした印象は、ベガーズ・オペラのファーストを思い起こさせもする。そう思わせる原因は実はギターのピーター・バンクスとキーボードのトニー・ケイによるものだろう。ピーターは決して下手なギタリストではないが、やりたい放題を尽くしてどこか曲のイメージを散漫なものにしてしまっている。トニー・ケイは逆に無難なバッキングに終始して、曲を印象付けるまでには至っていない。ただし、今述べたことはイエス・ミュージックとしての欠点であって、彼ら2人を非難するつもりは毛頭ない。逆に、デヴュー当時のこのメンバーだからこそ、私にとっては重要なアルバムに成り得ているとも言えるのだから。
オリジナル曲で私のお気に入りは「ルッキング・アラウンド」と「ハロルド・ランド」。前者はコンパクトにまとまったヒット曲という趣。後者はドラマチックな構成で70年代英国ロックの伝統的な曲調を持っている。他にも、「イエスタデイ&トゥディ」の弾き語り風ポップ・フォークなんてのは珍しいし(ビルのヴィブラフォーンが素敵だ)「スウィートネス」なんて甘いナンバーも後年の「スーン」とは違った歌物を満喫できる。
オリジナルのライナー・ノーツには、メロディ・メイカー誌のライター、トニー・ウィルソンが69年に伸びると思われる注目に値するグループはと聞かれて、1つはレッド・ツェッペリンを、そしてもう一つはイエスと答えた旨のことが書かれているが、歴史はそれが正しかったことを物語っている。
今回、紙ジャケになって再登場する「イエス・ファースト・アルバム」。改めて多くの人に聞いてもらい、その後の輝きの原点を再確認してほしいと願っている。
(H.G.Ref aka 後藤秀樹)
DATE(2001/5/31)
|