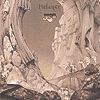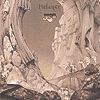なぜ「リレイヤー」は売れ残るのか?―――プログレ発展史からみるイエス試論
1.はじめに
ひょんなことで「リレイヤー」のレビューを担当することになってしまったが、実は本作は個人的には「危機」の次に好きなイエスの作品である。なんせ、イエスを初めて知った時点では最新作であった作品だ、当然、思い入れはある。
本論では、イエスの音楽表現のコンセプトとそれを実現させる過程における本作の位置付けと意味合いを、プログレという音楽ジャンルの発展史の観点から整理し、表題に掲げた「なぜ売れ残るのか」という問いへの回答を導き出そうと試みる。うまくオチがつくかどうかは、最後まで書けてのお楽しみ。
2.売れ残る「リレイヤー」
「危機」がいかに優れた作品であるかは、いろいろなところでいろいろな人が論じているので、いまさらここで論じることはしないし、本稿の目的でもない。イエス作品に限らず、現代のポピュラー音楽界における創造行為の成果として見てみると、「危機」は突出して優れた成果であることは間違いないであろう。まぁ、「別格」な訳ですね。となると、私としては、通常のイエス作品としては、「リレイヤー」が一番好き、ということになってしまう。
では、なぜ自分は「リレイヤー」が好きなのだろう・・・と考えてみる。本作の最も顕著な特徴は、「パトリック・モラツがキーボードで参加している」ということであろう。今まで、これが本作を好きな理由だろう、と考えていた。しかし、よくよく考えてみると、自分としてはモラツのプレイが特別好きなわけでもなく、ソロ作品も「ⅰ」しか聞いたことがないので、その音楽性が「リレイヤー」にどう反映されているのかも、よくわかっていない。
ところで、実は「ビッグ・ジェネレーター」以前のイエス作品はほとんどがLPでしか持っておらず、CDを買いなおしたのは、CDラジカセを買ったとき、初めて買ったCDであった「危機」と比較的最近買った、この「リレイヤー」だけである。しかも「リレイヤー」は紙ジャケ。今まで、紙ジャケといっても特別な関心はなかったのだが、「リマスタリングされて音質が向上」などと言われると、「あ、そうなんだ、知らんかった」という訳で、ひとつ試しに買ってみたのである。というか、これしか売ってなかったのだが・・・。
そういえば、今回は紙ジャケの再発記念なんですよね、このレビュー。確かに音質は向上しているようです。しかし、普通のCDは聞いてないので、その比較はできません。LPと比べると、だいぶんクリアになったような印象をうけましたが、いかんせん、私の普段使っている再生装置を考慮すると、そのような比較論はナンセンスだと断言します。つまり、違いなんかわからんような貧弱な装置なのね。とほほ。
それはさて措き、店頭で「リレイヤー」の紙ジャケを見つけたときは、ちょっと内心小躍りして「おお、これは貴重なものをゲットできたぜぃ」と喜び勇んで買ったものだ(というのは、紙ジャケは今や貴重品でプレミアすらついている、という情報だけがインプットされていたからです)。しかし、冷静に見ると、「リレイヤー」の紙ジャケだけは、そこらへんに当たり前のように売っていて、ちっともめずらしくないという事実に気がつくのに時間はかからなかった。 「なんや、結局売れ残ってるんかい」ということである。
「リレイヤー」が売れ残っている!自分としては、この事実に何か納得がいかない義憤のようなものに駆られ、その理由を考えてみた。そこで辿り着いたのが、冒頭に述べた本作最大の特徴「パトリック・モラツがキーボードで参加している」ということであった。いや、ひょっとしたらメーカーの生産計画にミスがあって(生産数の指示を一桁間違えたとか)「リレイヤー」だけ、非常に多量に生産してしまい、流通在庫として残っている、ということも考えられなくはない。それがために生産計画担当者が上司に叱責を喰らったかもしれない。いや、レコード会社がどんな生産体制になっているかは知らないので、ええ加減なことを言ってますが、通常、メーカーであれば、こんなこともありますよね。そんなことはどーでもいいや。
3.「リレイヤー」の独自性・・・語られうる混沌(カオス)
モラツが参加しているということは、70年代のイエスにとっては決定的な問題が存在する。すなわち、ウェイクマンが参加していない、ということである。当たり前か。いわゆるイエスがイエスとしてのステータスを確立したのが「こわれもの」だとする(異論はありましょうが)、そして、一旦その歴史に幕を下ろしたのが「ドラマ」だとする(これまた異論はあるでしょうが)と、この間、参加したキーボーダーは3人、すなわちウェイクマン、モラツ、ダウンズである。しかしながら、後者2名はそれぞれ一作ずつの参加で、しかも、その2作はどうやらファンの間では評価が分かれているようである。
一般的に本作の評価は「アバンギャルド」で「難解」なので「とっつきにくい」というものであるようだ。確かに、「危機」で表現されてきた「調和のとれた世界観」とは異質の混沌とした、荒々しいサウンドが大半を占めている。「危機」をコスモスとすれば「リレイヤー」はカオスである。明と暗、ハレとケといってもよいくらいの対照を示している。密かに、私は「リレイヤー」は「『危機』の弟」と呼んでいるのだが、先日某所でそう発言したところ、結構賛同してもらえたので、そう感じている人も多いのだろう。
とはいえ、「カオス」の表現とはいっても、演奏しているのはイエスなのだから、真性カオスになるはずもなく(例えばドイツのバンドのようなカオス表現)、あくまで語られうる枠組みの中でのカオス表現であるので、そこらへんが中途半端ではあるが、それは彼らの方法論だから、是とすべきであろう。その方法論いついては後述する。
要は、いかに「錯乱(の扉)」状態を表現しても、そこにはイエスの一貫したコンセプトと方法論は健在であり、本作を「アバンギャルド」と評するのは、あまりに表面的で本質を説明していないということである。なんか偉そうだな、ごめんね。
ところで、私は、イエスの基本はアンダーソン―スクワイヤ・ラインだと思ってずっと聞き続けていたので、「ドラマ」はともかく「リレイヤー」の評価が低いのは(というか売れ残っているのは)、極めて意外であった。(いや、「ドラマ」が優れた作品であることは十分承知しておりますし、アンダーソン不在がゆえにイエスではないなどというのは暴言だと思いますが)ところが、どうもそれは認識が誤っているのではないか、と今は考えている。
その認識の誤りを糺すには、イエスという一バンドとプログレという音楽の発展と変遷の歴史を回顧した上で、論点を整理する必要がある。
4.イエスの目指したもの・・・音楽的ダイナミズムの表現
イエスの歴史を概観するに、デビュー以来、メンバーチェンジを繰り返しながら、その音楽の独創性と演奏技術、作曲技法などを徐々に高度化、複雑化してゆき、遂にポピュラー音楽史上、前人未到の境地までに進歩し続けてきた彼らの音楽表現が最も先鋭的な形で花開いたのが、「危機」であることは論を待たないであろう。恐らく、彼らの音楽表現上のコンセプトは限られた編成で(いわゆる)クラシック的壮大さと複雑さ(もうちょっと具体的に言うと、ストラビンスキーなどの20世紀クラシックの壮大さと複雑さ。なぜストラビンスキーかというと、「リレイヤー」の解説書に当時のメンバーの一問一答が掲載されているが、アンダーソンは影響を受けたアルバム(アルバムぅ?)としてストラビンスキーの名を挙げているし、ライブのオープニングがあれでしょ、あれ)を表現しようとしたのではないか。 彼らの演奏するポリリズム的楽曲も、例えばジャズの世界のそれというよりは、ストラビンスキーっぽい。ハードなパートでも、そのハードさはいわゆる「ロック」的な剛球一直線というより、オーケストラの楽曲っぽいダイナミックな趣きがある。
ところが、例えばELPなどの方法論であるクラシックの楽曲の主題なりメロディーなりを流用(というかアレンジ)して自らの表現にするのとは違い、一つの楽曲(しかも長い)の中における主題の提示、展開、変奏、再現など、モチーフの操作に関して実に「クラシック」的な手法を採っている。ここがイエスの独特の個性になっている。クラシック的手法を援用してはいるが、アウトプットは極めてロックっぽく(そもそも彼らはロックミュージシャンなのだから)聞こえることになった(と思う)。(余談だが、ミュージシャンの資質がだいぶん違うので、印象はかなり異なるが、ELPの「タルカス」「悪の教典」なども同様の手法によっていると理解している。音楽表現のダイナミズムを追求してゆくと、やはりストラビンスキーあたりの音に行き着いてしまうよね。あれほどの動的音響を表現した音楽は、恐らく空前でしょう。19世紀には、あれほどの大掛かりな編成のオーケストラ曲はすくなかったでしょう)。
こういった意味でイエスをシンフォニックと呼ぶのは適切であると思う。いわゆる「シンフォ系」というのとはちょっと違うだろうけど。しかし、イエスはあくまでロックバンドであり、クラシック音楽とは違う。根本的な相違点があるとすれば、20世紀のクラシックは、オーケストラを大編成にすることをその重要な手段としたが、イエス(プログレ・バンド)はあくまでロックバンドの形態(コンボ編成と言ってしまおう)でそれを実現しようとした点である。そして、少人数であればあるほど、演奏者にとっては、その価値は高まったという可能性も否定できない。もちろん、これは電気楽器のテクノロジーの発達と不可分のムーブメントである。しかし、両者の目指すところに大きな隔たりがあったとは、どうしても思えないのである。
先ほど、引き合いに出したELPもそうであるが、ロックにおける音楽表現のダイナミズム(なんかよく分からん言葉だけど、他の適切な言い回しが思いつかないので)の追求が、プログレの短い発展史における重要なテーマの一つであったことは、恐らく間違いないだろう。もちろん、他にもテーマはあったと思うけど、それは措いといて。なんか、分かりきったことを述べるのに大幅に紙面を使ってしまったなぁ。
これは換言すれば、次のように要約可能である(いささか暴論ではあるが)。すなわち、「プログレ(シンフォニック・ロック)の歴史は、あらゆる音楽表現でこれまでなしえなかったダイナミズムの獲得の歴史である」と。
さて、延々とわかったようなわからんような愚論を述べてきたが、やっとここから本論です。長い前振りですなぁ。もう力尽きたよ。じゃあね。
5.コンセプト実現のための方法論
あいや、気を取り直して、もうちょっとお付き合い願います。
何かの雑誌で「世界最小のオーケストラとはマハビシュヌ・オーケストラに捧げられた献辞であるが、それは実はイエスにこそふさわしい」というようなことを誰かが書いていたが、確かにそれは言いえて妙だと思う。繰り返しになるが、イエスは5人という小編成のバンドで、オーケストラ並みの複雑でダイナミックな音楽表現を目指していたのである。恐らく、それはアンダーソンの目指すところでもあったのだろう。当然ながら、そのような音楽を目指すとなると、演奏者各人の技量とコンセプトへの忠実さがシビアに問われることとなる。どんなに早く巧くギターが弾けても、バンドとして目指すアンサンブルの一部として機能しないプレイヤーは不要なのである。おそらく初期に脱退(クビ?)したメンバーはそういった点で問題があったのではないかと推察する。
また、逆にハウのような「生涯一ギタリスト」的な職人肌のミュージシャンが、このようなバンドのコンセプトに忠実に従い、アンサンブル主体の演奏に徹したことは賞賛に値する。通常なら、猿のように弾きまくって、悦に入るタイプのような気がするのだが、実際はそうでもないようだ。これは、ライブの場において弾きまくりの機会を与えられていたから、なしえたことかもしれない。
そして、プログレに限らずロック全般にそうであるが、電気楽器のテクノロジーの進歩を抜きにして、その音楽表現について語ることは、ある意味で不備であろう。特にキーボードについてはプログレ発展史の中で重要な役割を果すので、要注目である。キーボードほど、プログレ発展期に進歩した楽器はない。そして、小編成のバンドでオーケストラみたいな音を出そうと思えば、キーボード類は必須であり、しかもその演奏者及び機材によって、アウトプットは大いに左右される。ギターやベースは、誰が弾いてもギターやベースの音しかしないが(最近はギターシンセを使う人が増えているので、必ずしもそうではないが)、キーボードとりわけメロトロンやシンセサイザーなどの電子楽器は、いろいろな音が出せる。今から考えると、至極当たり前のことであるが、それ以前にはピアノとオルガンくらいしかなかったことを考えると、これは画期的なことであったと推察される。
ケイがイエスをクビになったのは、シンセサイザーなどの電子楽器を嫌ったからだそうだが、なるほど、アンダーソンの目指す音楽表現を実現しようとすれば、それももっともな話である。ケイの後釜にバンドが据えたのは、山のように機材を積み上げ、多彩なサウンドを作り出せるマルチ・キーボーダーの権化のような男、ウェイクマンであったのは、その意味で必然だったのであろう。「こわれもの」以降の数々の名曲、名演でイエスのキーボード=ウェイクマンという図式ができ上がってしまったようである。確かに、長い金髪をなびかせ、ひらひらのついたマントみたいな服を着てキーボードの山に向かう姿は、当時のイエス・サウンドの象徴とも言えそうである。つまり、なんか華やかで煌びやかな感じ。
6.イエスにおけるプレイヤーの役割分担・・・アンダーソンはナポレオン?
そんな訳で、イエスのクラシック的部分を担っているのがウェイクマン、と理解しがちだが、必ずしも、そうでもない。彼の弾くフレーズは、確かにクラシカルな修飾音の多いものであるが(たとえば「シベリアン・カートゥル」の中間部)、それはあくまで断片であり、イエスがシンフォニックたる理由の中核をなすものではないことは、ここまで読んでくださった方なら御理解いただけるものと思う。
ロックバンドであるイエスの演奏局面での主導権は、少なくとも70年代中期から一時解散までは、スクワイヤのベースが握っていることは恐らく間違いない。ホワイトの粗雑なプレイも、スクワイヤがリードすることで、豪快な印象となり、全体としてプラスに働いていると思う。そして、バンド・アンサンブルの中核がリズム体である、という認識は、実はアンダーソンが明確にヴィジョンとして持っていたことは注目に値する。
「・・・だから歌詞的には徹底的に透明感の強い、天上界のようなものを目指しているんだ。それに機動力を持たせてくれるのが、このグレイトなリズム・セクションだと」(ロッキング・オン1992年の8人イエス来日時のインタービューより)
そういった面でも、バンドとしての在り方を明確に意識して、コントロールしていたのはアンダーソンであった。そして、バンドの肉体であるメンバーを演奏の局面において、ドライブさせていたのはスクワイヤであった。いわば、アンダーソンが大脳でスクワイヤが小脳であったのだ。これは前述のインタビュー記事で、次のように語られている。
「うん、そうだよ。でもそういう時には、僕がいつだって指揮者として振る舞ってきたんだ。つまり、僕がナポレオンなのさ!」
「だから何かおかしくなったら、僕が『アラン、君がそう叩いちゃうとビルがぎこちなさそうだから、そこは抜きにしてくれよ』とか『リック、ここでトレバーをバックアップしてくれよ』とか言ってみるわけだね。すると皆演ってくれるんだよ。・・・『さもないとジョンがまたふてくされて面倒だからなあ』とか『全くたまらないぜ』って(笑)。でもそれが僕の仕事なんだよ」
また、余談であるが、8人イエスの来日時にブラフォードがメンバーからはずされかかったそうである。この時も、ブラフォードはずしを画策する他のメンバーを牽制し(よっぽど嫌われていたのだね)、強引にブラフォードを参加させたのは、アンダーソンであった。(「ビルが来ないのなら、ボクも行かないっ!」とごねたらしい)これは、もちろんABWHでの経緯もあるのだろうが、アンダーソンのリズム体に対するこだわりを感じさせるエピソードではある(その割りに、ABWHで活躍していたブラフォードの相棒、トニー・レビンに対しては冷たい。これぞイエスの、またはアンダーソンの排他性の顕れであろう)。
アンダーソンのリズム体重視は、これまで延々と述べてきた彼らのコンセプト、「音楽的ダイナミズムの表現」を視座に据えると、極めて当然のバンド観である。
7.「リレイヤー」・・・殺戮と復讐の物語
このような表現欲求、バンド観を持つ、リーダー(と敢えて言ってしまおう)を戴くバンドにおいては、キーボード・プレイヤーの役割はどんなであったか。まさしく、肉体に対する衣装のようなもので、表現する対象によって変幻自在にそのスタイルを変えられる柔軟性と応用性を求められる。そして、それは「こわれもの」においてそのプロトタイプを示し、「危機」で完成する表現されるべきテーマ、すなわち「精神の遍歴の果てに辿り着いた全体と個の合一による調和と法悦の瞬間」を表現する音楽的ダイナミズムの創造で、一応の完結をみる。(あ、「全体と個の合一による調和と法悦の瞬間」って、私がそう感じて勝手に言っているだけで、メンバーがそう言った訳じゃないです)
このようなテーマを扱うには、ウェイクマンの擬似クラシック的壮大さ(「はったり」とも言う)は、大いに有効であった。調和のとれた端正さ、上品ではあるが、それでいて、軟弱にはならない壮大なスケール感。ウェイクマンの持つ表現者の資質が、見事なまでに作品のテーマに合致し、バンドの骨格である繊細にして豪快なリズム体との相乗効果で、希代の名作となったのである。
「危機」において完成されたスタイルを次作「海洋地形学の物語」では、さらに規模を拡大して更なる高度化を図ったが、結果としては「危機」では凝縮されていたがために醸し出されていた極度の緊張感が希薄になり、全体に散漫な印象となっている。部分的には、目の覚めるような刺激的なパートもあるのだが。本作を省みると、ウェイクマンのスタイルでは、次のステップとしてアンダーソンが画策したテーマの表現において有効に機能するかは、いささか疑問に思われる(これって、野球評論家のよく言う結果論ってやつだね)。
とにかく、表現の進化のスピードを緩めることをせず、イエスはさらなる高みを目指して進撃を続ける。その結果、もっと厳しく、激しく緊張を強いられるような表現を目指していくこととなる。それというのも、次作のテーマは「破壊と殺戮、蹂躙と復讐、その混沌の果ての勝利」という「危機」のある意味で神秘主義的な曖昧さを含んでいたものとは趣を異にする、非常にアグレッシブなものだからである。
次作のテーマがこのようなものになることを知っていたのかどうかは不明だが、ウェイクマンは「リレイヤー」の制作を待たずに脱退してしまう。しかしながら、この選択は、間違いなくウェイクマンにとってもイエスにとっても最良の選択であった。ウェイクマンのスタイルでは、このような攻撃的なテーマを表現するのに適したイディオムを持っているとはとても思えないし、そもそも彼のスタイルの限界を前作で垣間見せてしまっているので、これ以上の更なる表現の先鋭化は望めないと判断するのが適切であったろう。ウェイクマンの後任はヴァンゲリスに決定していたという話なので(イギリスのミュージシャン・ユニオンの問題があって参加できなくなったと聞く)、恐らく、アンダーソンにはウェイクマン抜きの新イエスのヴィジョンは明確にあったのであろうと推察される。
結局、どのような経緯があったのかは詳らかでないが、モラツを迎えて、制作された「リレイヤー」は、これまでのイエスにあった、どことなく中途半端なクラシカリズムというか衒学趣味というか、そういうウェイクマン的な冗漫さを排した、非常にシャープでスリリング、贅肉を削ぎ落とした力石徹のようにストイックでありながら、同時に楽想において「危機」をも凌ぐ豊潤さ、あたかも眼前で甲冑に身を包み槍をかざした重装騎士団が刀を交え、燃え盛る火の中で非武装の婦女子が泣き叫ぶ様が見て取れるがごとき音楽表現のダイナミズム、まさに前人未到の境地にまで達したのである。
この成果をもたらしたものは、もちろん従来のメンバーの技量ではあるが(前作よりさらに技術的に向上しているのが驚異的である)、最大の功労者は、電子ピアノのシャープなタッチ、派手にベンディングし倒すムーグのソロ、複雑なハーモニー感のコードワーク、ウェイクマン的クラシカリズムを徹底的に排したポストモダン的アプローチ等々の面で多大な貢献をしたモラツであるといえる。そして、モラツの活躍が本作の最大の聴き所でもある。
ちなみに、前述の「リレイヤー」の解説書に掲載されている質問票によれば、モラツの「音楽的影響」欄の回答は「ストラビンスキー、ジミ・ヘンドリックス、ビートルズ、ラフマニノフ」と書かれてある。やはり、この人もストラビンスキーが好きだったようだ。
そして、さらに妄想をたくましくすれば、本作のドラムがブラフォードだったら・・・というのは、イエスファンならば、誰もが一度は思ったことであろう。ううう、そのラインナップで、一度やってほしいなぁ。無理だろうなぁ。しかし、案外、ホワイトの粗雑なプレイが、曲の破滅的なイメージにあってたりするかもしれん。
8.なぜ「リレイヤー」は売れ残るのか
ところが、皮肉なもので、このような目覚しい成果を実現した稀代の傑作の紙ジャケが売れ残ってしまうという驚くべき事実。そう、「危機」にあって「リレイヤー」にないもの、それはウェイクマンのキーボードプレイである。(ブラフォードのドラムもないけど、それは、もう叶わぬことだから、諦める)先に少し述べたが、「イエスのキーボード=ウェイクマン」という図式は私の想像以上に強固なものとして、ファンの心理に根付いているらしい。イエスファンの少なくない数の人々は、ウェイクマンの擬古的でスノビッシュなプレイを支持しているらしい(別にウェイクマンがそんなに嫌いな訳ではないです)。まぁ、そんなの人の好き好き勝手だから、だからどうだとは言わないが、それがためにこの稀代の傑作「リレイヤー」が売れ残っているとすれば、非常に残念なことである。
ところが、これを我が身に照らして考えると、まったく逆の事態に立ち入ってしまう。つまり、ウェイクマンの擬古趣味って、ちょっと鬱陶しい、と思ってはいるのである。曲によっては、それがプラスに働いて、効果ありのケースも多々ありますが・・・。
きっと、「こわれもの」に収録されているブラームスがいかんのだろう。なんであんなものをわざわざイエスの作品に収録したのかなぁ。イエスの歴史上、もっともなくてもよい曲でしょうね。「イエスイヤーズ」にでも初出で収録されたら値打ちもちょっとはあったかもしれないが。他になにかやることはなかったんかい、と言いたくなる。あれのおかげで、ウェイクマンの印象は基本的に良くないです。
これまで論じてきたことからすると、アンダーソンの鉄壁のコンセプトからはみ出た、まぁ、良くも悪くもウェイクマンの手癖のような、尾てい骨のような盲腸のような、そんなような、ものの本質とはまったく関係ないものが、イエスの、アンダーソンの心血を注いで実現した前人未踏の音楽表現の正当な評価を妨げているとしたら、まことに嘆かわしいことである。真摯なイエスファンの方々はそんな枝葉末節に惑わされてものの本質を取り違えるようなことはないと思うが、それにしても、なぜ売れ残っているのだ、「リレイヤー」・・・。
7.「リレイヤー」発表当時のプログレ状況
これで本論は終了しているのだが、ちょっと興味深い記事が手元にあるので、引用しておく。ピンク・フロイドの「炎」のライナー・ノーツなのだが、ここで1975年当時のプログレの状況を簡単ではあるが概観している。パンク登場前夜の、閉塞したロック界の様子が垣間見える。
記事は大貫憲章氏といまいずみひろし氏の対談である。
い:『アウトバーン』なんかアメリカで随分売れたようだけど、元タンジェリン・ドリームのクラウス・シュルツという人はあれがアメリカでベストセラーになったおかげで、アメリカにおけるシンセサイザー・ミュージックの聞き方みたいなものが固定されてしまったんじゃないかと心配しているそうだ。
大:うん、いわゆるコミックとして聞くという聞き方ね。(略)ま、プログレッシブ・ロック・シーンというものが今方向を見失っているような部分があるのは確かだと思うし、キング・クリムゾンが解散してしまったのは顕著な例だと思うけど、(略)
い:現在のプログレッシブ・シーンを見ているとイエスはなんだか釈然としない、テクニックばかり身に付けようとしている感じもあるし、キング・クリムゾンは解散してしまって、ロバート・フリップは今後どうやっていくのかを考えているような節がある。(略)(1975年9月)
ふーむ、イエスは「リレイヤー」発表したところなので、上記のうちイエスに言した部分が、当時の日本のロック・ジャーナリズムの基本的認識だったのだろう。大貫憲章氏といえば、当時のロック・ジャーナリズムの中では大きな影響力を持った人だったから、この見解は、一般のロック・ファンの基本的認識でもあったであろう。
つまり、イエスはテクニック至上主義的作品(「リレイヤー」のことだね)を発表し、なんだか理解不能な世界に行っちゃったしねぇ、なんだか、プログレもだめっぽいな。と、そんな陰の声が聞こえてきそうですな。
8.「リレイヤー」以降のイエス
本作以降、彼らの音楽表現は過剰な部分が整理され、シェイプアップされたコンテンポラリー・ハードロックに向かってゆくことになる。そして、演奏者の肉体性に多くを依存していた彼らの演奏技術を含む音楽的ダイナミズム表現が(これはある意味で極めて古典的手法ではある)、テクノロジーに基礎を置く、現代的表現に変質していくのも、本作以降に顕著になった傾向であろう。ま、要するに、これまでの手法でやれることはやり尽くした、という感じでしょうか。で、新たな方法論を模索し始めたのが次作「究極」からだと。
そして、ついにアンダーソンの脱退によって、彼の鉄の意志とスクワイヤをはじめとするメンバーの個性と演奏技術に支えられてきたイエス・ミュージックは、その魔力を一気に失ってしまうことになる。
そして、「ロンリー・ハート」の大ヒットによって再びロック・シーンに帰ってきたときは、優れたポップ・ソングを制作する職人的ロックバンドになっていたのである。
こうして、イエスの歴史を回顧して、プログレなる音楽の発展史と重ね合わせて見てみると、どうやらミューズに遣わされたロックの神さまは1975年ごろには天井に帰ってしまっていたらしい。およそ10年ほどの短い降臨期間であったようだ。
最後まで、お付き合いいただき、まことにありがとうございました。
(よたろう皇帝)
HP:よたろう帝国
DATE(2001/6/13)